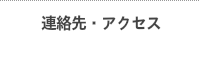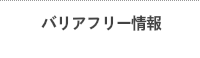パイパーズ2012年4月号「お客さんは全ヨーロッパのフルーティストたちです。」
音を言葉でどう表現するか
EメカとH足部管の割合が増えて来た
楽器の質量と響きの問題
音が明るい・暗いという言葉
(東京フルートスペースを開く前、欧州で仕事をしていた頃のインタビュー記事です)
——野村さんのお仕事を簡単にご説明ください。
野村 商品の開発とアーティストサービスが一番の大きな柱です。アーティストサービスというのは、プロの演奏家の楽器のメンテナンス、何かあったときの修理、改造やカスタマイズなども含まれます。
——お客さんは欧州全域にわたるのですか?
野村 はい、ロシアを除く欧州全域です。北は北欧から南はギリシャ、トルコあたりまで入ります。
——とすると、フルーティストと対面でお仕事をされるより、楽器は送られて来ることが多いわけですか?
野村 送られて来ることが多いのはもちろんですが、飛行機や車でアトリエに来られる方もいますし、内容次第ではこちらから積極的にお伺いする場合も少なくありません。とくに新しい楽器を試奏するような場合、ふだんリハーサルやコンサートをやる環境の中で判断したいと思われる方が多いので、私の方から出向くことはよくあります。
音を言葉でどう表現するか
——今日まずお聞きしてみたいのは、人によって、あるいは国によって音色に対する考え方は違うでしょうし、表現する言葉も違うのではないかと思うのですが、その辺はどのように対応していらっしゃるのか、ということなんですが。
野村 一つの言語を話す国や民族が全員おなじ表現をするとは限りませんし、個人によってもだいぶ差はある気がします。
試奏の時に私がいつも気をつけているのは、その人が使う言葉や言い回しと、実際に吹いて聞かせて下さる音との相関関係をまず把握することですね。言っている言葉と実際の音に違いを感じたら、それがどういった違いなのか、自分だったらそれを言葉でどう表現するか、そうしたことをいつも考えるようにしています。言葉といっても、プレイヤーの方は聴覚以外の感覚、味覚、触覚、嗅覚、視覚などに喩えることもとても多いのですが。
——ヤマハの「イデアル」を一緒に開発されたアンドラーシュ・アドリアン氏などはどんな風に?
野村 アドリアンさんの表現はとても明確で分かりやすく、発音が良い、悪い、響きが大きい、小さいなど、よい意味で即物的な表現をよくなさいます。ただし、その先の話になると、味覚、たとえばワインのテイストで表現されたり、響きのきめ細かさなどを触覚に近い言葉で話されたり。
——異質な文化に属するものの微妙な喩えなどは、理解するのが難しくありませんか?
野村 難しいのは確かですが、音楽もその国の土壌や文化の中から出て来たものですから、逆に言えば、感覚的な比喩や表現の方が直感的には分かりやすいですね。もちろん、そう感じられるようにこちらも努力しなければいけませんが。
EメカとH足部管の割合が増えて来た
——国によるピッチの違いが問題になることはないのですか?
野村 ピッチは特にイギリスとアメリカが低くて、コンサート開始時が440〜441くらいだろうと思います。ヨーロッパ大陸だと442〜443が多いでしょうか。しかしその程度の範囲なら、ヤマハの標準仕様である442で対応できると思います。もちろん特注でローピッチ仕様にすることも可能です。
フルートの仕様は、ヨーロッパではどこも似た傾向になって来ました。演奏スタイルが似通って来たことを反映しているのかも知れません。具体的に言えば、EメカとH足部管の割合が増えています。とくに若い世代にそれが顕著な気がします。昔はフランスなど、伝統的にEメカを付けないなどということがあったのですが。
——そうした傾向をどのように分析しますか?
野村 高音域で落ち着いた、明るくなり過ぎない響きが求められるようになったのが一つの理由かな、と個人的には思っています。オーケストラの他のセクションや指揮者などからそうした要求が多くなって来たのではないかと。それと、H足部管が付いていた方が、高音域の音程や響きをコントロールしやすいと感じる方も多いようです。
——足部管が伸びることで高音域に影響してくるわけですね。
野村 はい。Hが出るか出ないかということよりも、楽器全体の響きが変わり、音程感も若干変わるというのでH足を選ばれる方も多いですね。
——それでもC足部管にこだわる方もいます。
野村 もちろん、そういう方はヨーロッパにはまだ沢山いらっしゃいます。C足部管の方が楽器全体の響きがオープンになり、音色の変化が付けやすくなる、また高音域が少し高めになった方が表現しやすい、という方もいらっしゃる。もちろん、どっちが良い悪いの話ではありません。
——オフセットかインラインかという点はいかがですか?
野村 国によってオフセットかインラインかの傾向が分かれるというのは、単なる伝統の問題じゃないでしょうか。最近は楽器の質量が重くなる傾向にありますので、指や肩の負担を訴える方がいらっしゃいますが、そんなときに、もともとインラインだった方がオフセットに転向されたりするケースは昔よりは多くなったような気がします。
これも、オフセットの方が優れているということを言いたいのではなく、仮にH足部管を使うようになれば、当然、その分楽器は重くなりますから、その負担を軽減したいと感じる方が増えてくる、ということだと思うのですが。
楽器の質量と響きの問題
——野村さんが関わったヤマハの新しい「イデアル」は、キーの台座などいろいろなパーツでも質量を重くしていますよね。
野村 トーンホールを含めた管体とメカの部分が重めになっています。たぶん、昔よりもフルートにそうした響きを求める人が増えているのではないでしょうか。演奏者に限らず、指揮者も聴衆も。
——いわゆるダークな響きですね。
野村 ええ。密度の濃い、しっかりと芯のある、どちらかといえば暗めの音が求められることが多いのではないかと思います。ただ、イデアルの発表の時にもお話しましたが、単純に楽器を重くするだけだと、演奏しにくいと感じられる方が多くなります。音が飛ばなかったり、抵抗が増えたと感じられる方が多くなりますから、そこはバランスを取り直す必要が出て来ます。
——例えばルイ・ロットなどは軽い楽器ですが、オーケストラで使っている方もいますね。
野村 ルイ・ロットやそのスタイルを踏襲した楽器は、持つとすぐ分かるくらい最近の楽器よりも軽いですね。質量の軽い楽器は、物理的には抵抗が少ないことが多いのですが、こうした楽器は吹くと抵抗が強いと思われる方が多い。その抵抗感がどこから来るのかというと、そこには様々な要因があると思いますが、私はリッププレートを含めた歌口まわりの形状で、あの抵抗感を生み出していると思っています。
——歌口が丸く小さい。
野村 アンダーカットも少ない。息が入りづらいといえば入りづらいけれど、本体部分が非常に軽く、トーンホールが昔のスケールだと比較的大きめだったりして、楽器としてのバランスがそこで取れているように思います。あのくらいの質量の楽器で、クーパーカット以前のやり方で豊かな表現力を獲得しようとすると、そのようなバランスになるのかなと。
ただ、抵抗感というのは一つではありませんし、抵抗感の感じ方も一つではないと思います。
抵抗感を、吹いた時に楽器から返ってくるフィードバックだと定義するなら、広いポイントに向かってたくさん息を吹き込める感覚を持ちながら、しっかりした抵抗感が感じられる楽器というのは作れるはずなんです。どのダイナミックレンジでも楽器全体が効率よく鳴り、その鳴っている感覚が、フォルティシモでもピアニシモでもきちんと吹く人にフィードバックされてくる、そうした感覚も私は抵抗感の一つの形だと思っています。
つまり、吹き込んでも適度な抵抗感を作れる、というところにすごく意味があると思うんですね。アウトプットとして求められるのは、しっかりとした芯のある、どちらかというとダークな響きであるとしても、プレイヤーのインプットの部分ではとても自由であって欲しい、というのが最近よく聞かれる要望です。ヤマハのイデアルが高い評価を頂いているのは、そのへんもあるのでは、と私は分析しているのですが。
——吹きやすいけれど、芯のある豊かな響きが得られるということ。
野村 本当に吹きやすく、鳴るポイントが広い楽器でありながら、軽くなりすぎない豊かな響き。しかも、音量を絞っていっても音色はきちんと残るような。
——ポイントの狭い楽器を苦労して鳴らし、結果として美しい音色を手に入れるという方もいます。
野村 もちろん、そうやって素晴らしい結果を出されている方はたくさんいると思います。ただ、現在はオーケストラで特に顕著ですが、ホールが大きくなり、より広いダイナミックスを求められるために、すべての楽器で大きな音が求められるようになりました。それに合わせて楽器が開発され、進化して行くのは自然なことだと思います。
他の楽器がどんどん豊かな音量になっていく中で、世界中を忙しくツアーしてまわるような人たちにとって、「楽器のポイントの狭さを心配しないで済むなら、それにこしたことはない」という意見はよく理解できます。もちろん、それでもなお狭いポイントの楽器を使いこなされている方は素晴らしいと思いますが、そうではない需要も多いのです。
音が明るい・暗いという言葉
——「ダークな音色」が求められる傾向についてはどうお考えになりますか。
野村 ソリスティックな要素も必要だけれども、例えばオーケストラの木管セクションから浮き出てしまうような音は敬遠される可能性が高くなっているようです。奏者の耳元で聞こえる音も含めて、他の楽器と混ざりやすい音、そうした暗さ、柔らかさを持った音を求める人が多いように感じます。
——ダークというのは、高次倍音が少ないということですか?
野村 いえ、単純に高次倍音をカットしただけだと、どうしても物足りない要素が出てきます。他と混ざりやすい音であっても、必要なときは大きな音でホール一杯に聞こえないといけない。また豊かな色彩感も持たなければいけない。そのためには高次倍音というのは絶対に必要な要素です。
——「イデアル」の取材でアドリアンさんをインタビューしたとき、「金よりも銀のフルートの方が音に輝きがある」とおっしゃったのが意外でした。普通は逆にとらえる人が多いと思うのですが。
野村 私もインタビューに同席していて思ったのは、「輝きの種類が違うのかな?」ということでした。何を指して「輝き」というのかという問題だと思いますね。
金、銀といっても、様々な配合やオプションがあるので一概には言えませんが、一般的によく使われている925のスターリングシルバーと、14カラットのゴールドを例にとれば、シルバーで「輝きがある」という評価をその楽器が受けるとしたら、「銀特有の高次倍音の聴き取りやすさを指していることが多い」というのが聴き手としての私の印象です。それと、銀のフルートの特性でもある音の拡がり方、この二つがミックスすると「輝き」として聞こえることが多いと思います。
一方で、14Kが輝いているという評価を受けたときは、やや抽象的ですが、「金の持つ響きの明晰さ」を指していることが多いのではないでしょうか。響きのクリアさと言ってもいいでしょう。私は14Kの高次倍音は弱いとは思いませんけども、他の仕様がすべて一緒だとして、銀よりも金の輝きの印象が弱いとしたら、基音や低次倍音が金の方が聞き取りやすいからなのか、と思ったりします。
音が明るい、暗いというのがいかに曖昧な言葉であるかは、プレイヤーの方ともよく話すことです。何か一点の数値を示してこうだと決めることは出来ない。響きの印象の総体として受け取っていますからね。同じ場所で1本の楽器を同じ人が試しても、(吹き手・聴き手)二人の明るい・暗いの印象が逆になることがあるんですよ。ですから、プレイヤーさんから印象を聞かれたときは、出来るだけ「明るい・暗い」という以外の表現を含めてお答えするようにしているんです。
——金を買ってもらった方が、営業的にはありがたいわけですよね(笑)。
野村 いえいえ、「あいつは金しか勧めない」となるとお客さんとの信頼は築けません(笑)。どんな仕様のものでも、幾らの価格のものでも、自分が一番いいと感じたものをお答えするようにしています。
——野村さんのお仕事は、よくF1ドライバーをサポートするピットの技術者に喩えられるように、アーティストに寄り添い、その人のコンディションまで見極めながら、細かな要望を聞いて結果を出す。大変なお仕事ですね。
野村 芸術家のみなさんも人間ですから、日々のコンディションもいろいろだと思います。私としては、調子が悪い日なら悪い日なりに、その状態を把握していくことが大事なんですね。
その上で、その方が楽器を試される場合など、ある環境の中でこの楽器とこの楽器を比べたらどのように違ったということを率直に申し上げ、アーティストの方と一緒にベストのものを探していくのが、作り手としての自分の役目だと思っています。それに対してどんな判断を下されるのか、何を決断されるのかはアーティストの方それぞれが決められればいいことです。そうしたことを、出来るだけ良い環境で判断していただくためのお手伝いが出来れば、と思っています。
(株式会社杉原書店様のご厚意によりパイパーズ2012年4月号/No.368より転載。→出版社公式HPへ)
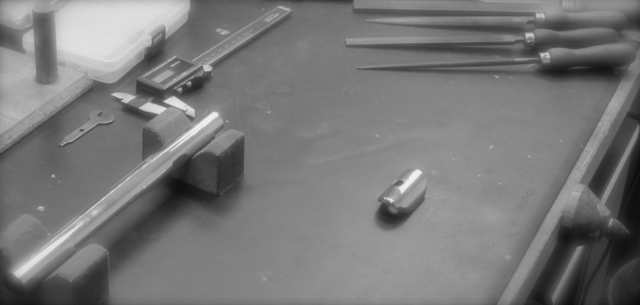
2011年頃にアメリカのメジャーオーケストラ首席フルート奏者からの依頼を受けて製作した14K頭部管。